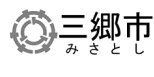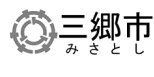| 事務事業名、担当課等 |
| 事務事業コード |
1000104 |
| 事業名 |
洪水ハザードマップ策定事業 |
総
合
計
画
の
位
置
づ
け |
まちづくり方針 |
1 安全でいつも安心して住めるまちづくり |
担当部名 |
危機管理監 |
| 担当課名 |
危機管理防災課 |
| 施策の柱 |
1-1 災害から市民の生命と財産を守る |
開始年度 |
令和3年度 |
| 終了年度 |
なし |
| 施策 |
1-1-2 風水害対策の強化 |
| 施策の目的 |
対象 |
市民、市内全域 |
| 意図 |
・減災への対策が進むことで、最小限の被害に抑えられる |
| 事務事業の目的、概要等 |
何をする事業か
(概要) |
生活空間である市街地の電柱などに河川が氾濫した場合の想定浸水深等の情報を標示する「まるごとまちごとハザードマップ」を導入することで、自分たちが生活する地域の洪水の危険性を実感してもらい、日頃からの水害に対する備えの啓発と危機意識の醸成に努める。
|
何の為にやるのか
(目的) |
平時から水害発生時の危険箇所や避難場所について正確な情報を広く周知することで、水害発生時に安全かつ的確な避難行動が行えるよう、市民一人一人の防災意識を高めるため。
|
誰・何に対する
事業か
(事業の対象) |
市民
|
目的達成のため、
事業の対象を、
どうしたいのか
(目指す成果) |
大河川等の氾濫に対する危険度を認識していただき、災害時の備えや避難行動に役立てる。
|
| 課題 |
様々な言語への対応
|
| 対応 |
ニーズの把握
|
| 目的を達成することで、市がどうなるか(事業の意義) |
災害に対する知識が深まり、地域防災力が向上する。
|
| 歳出 |
| 総事業費(合計) |
実績
|
| 令和3年度決算
|
| 2,170,000
|
| 歳入 |
| 特定財源 |
実績値
|
| 令和3年度決算
|
| 特定財源計 |
0
|
| 市の実質負担額(=総事業費−特定財源) |
2,170,000
|
| 業務分析(量と質) |
|
4〜6月 |
7〜9月 |
10〜12月 |
1月〜3月 |
特記事項 |
| 人員(担当) |
フルタイム |
2 |
パートタイム |
0 |
フルタイム |
2 |
パートタイム |
0 |
フルタイム |
2 |
パートタイム |
0 |
フルタイム |
0 |
パートタイム |
0 |
|
業務割合推計
(当該事務/係全体事務×100)
【勤務時間】 |
5% |
0% |
5% |
0% |
5% |
0% |
0% |
0% |
| 定型・非定型業務 |
定型業務 |
定型業務 |
定型業務 |
|
| 業務の難易度 |
普通 |
普通 |
普通 |
|
| 活動指標 ※市が何をするか |
| 指標名 |
標識の設置箇所数 |
| 単位 |
箇所 |
指標数値のめざす方向 |
増加 |
| 目標値 |
200 |
| 目標進捗 |
計画値 |
実績値 |
|
達成率 |
所見 |
| 令和3年度 |
200 |
130 |
箇所 |
65.0 |
% |
「主要道路、公共施設、公民館、過去に浸水が発生した地域」の付近を基準として、必要数を選定した。 |
| 令和4年度 |
|
|
箇所 |
|
% |
|
| 令和5年度 |
|
|
箇所 |
|
% |
|
| 令和6年度 |
|
|
箇所 |
|
% |
|
| 令和7年度 |
|
|
箇所 |
|
% |
|
|
|
|
箇所 |
|
% |
|
| 指標値の算定・把握方法 |
指定避難所33箇所+自主避難場所7箇所 合計40箇所の周辺の街区を中心に5基ずつ設置する。40箇所×5基=200箇所 |
| 成果指標 ※市民(市)がどうなったか |
| 指標名 |
|
| 単位 |
|
指標数値のめざす方向 |
増加 |
| 目標値 |
|
| 目標進捗 |
計画値 |
実績値 |
|
達成率 |
所見 |
| 令和3年度 |
|
|
|
|
% |
|
| 令和4年度 |
|
|
|
|
% |
|
| 令和5年度 |
|
|
|
|
% |
|
| 令和6年度 |
|
|
|
|
% |
|
| 令和7年度 |
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
% |
|
| 指標値の算定・把握方法 |
|
| 事業の評価・改善/実績報告 |
| 実績報告 |
〇まるごとまちごとハザードマップの設置
平時から水害発生時の危険箇所や避難場所について正確な情報を広く周知することによって、いざという時に安全かつ的確な避難行動につなげ、被害を最小限にすることを目的に、生活空間である市街地の電柱などに河川が氾濫した場合の想定浸水深や避難場所等の情報を標示する「まるごとまちごとハザードマップ」を設置した。また、設置した場所の位置図及び概要について、市ホームページにて公表した。
【設置数】
・電柱…103ヵ所
・小中学校…27ヵ所 |
| 評価 |
当初の予定通り、12月に全ての箇所への設置が完了した。
住んでいる地域のより身近な情報を得られるよう、第二大場川を境に中川に近い地域は中川、江戸川に近い地域は江戸川の想定浸水深を標示した。 |
| 今後の方針(改善策) |
標示内容の多言語化、想定浸水深に応じた避難方法の啓発等に取り組んでいく必要がある。 |
|