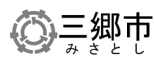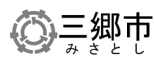| 事務事業名、担当課等 |
| 事務事業コード |
1000971 |
| 事業名 |
いじめ不登校対策事業 |
総
合
計
画
の
位
置
づ
け |
まちづくり方針 |
2 子どもが健やかに、のびのびと成長できるまちづくり |
担当部名 |
学校教育部 |
| 担当課名 |
指導課 |
| 施策の柱 |
2-2 子どもや若者が学び、健やかに育つ環境をつくる |
開始年度 |
平成19年度 |
| 終了年度 |
なし |
| 施策 |
2-2-1 質の高い教育及び環境の充実 |
| 施策の目的 |
対象 |
小・中学生 |
| 意図 |
・生きる力をすべての子どもが身につけている |
| 事務事業の目的、概要等 |
何をする事業か
(概要) |
教育相談、いじめ撲滅運動(児童会・生徒会)の支援
|
何の為にやるのか
(目的) |
心の教育の推進と教育相談体制の充実を図るため。
いじめ撲滅運動(豊かな体験活動)の充実を図るため。
|
誰・何に対する
事業か
(事業の対象) |
市内全小中学校(27校)
|
目的達成のため、
事業の対象を、
どうしたいのか
(目指す成果) |
いじめの根絶、不登校児童生徒を削減する。
|
| 課題 |
いじめ撲滅運動における取組がマンネリ化しつつある。
|
| 対応 |
新規の取組を計画に取り入れるよう支援する。
|
| 目的を達成することで、市がどうなるか(事業の意義) |
安全・安心な学校教育が推進され、児童生徒の生きる力を育むことができる。
|
| 歳出 |
| 総事業費(合計) |
実績
|
| 令和4年度決算
|
| 960,760
|
| 歳入 |
| 特定財源 |
実績値
|
| 令和4年度決算
|
| 特定財源計 |
0
|
| 市の実質負担額(=総事業費−特定財源) |
960,760
|
| 業務分析(量と質) |
|
年間 |
特記事項 |
| 人員(担当) |
フルタイム |
1 |
パートタイム |
0 |
市内全小学校に月1回、全中学校に月2〜4回スクールカウンセラーを1名配置し、児童生徒・保護者とのかかわりをとおして学校の教育相談体制を支援している。市内全中学校にさわやか相談員を1名配置し、教育相談業務に携わっている。市の担当職員は学校と連携を図っている。 |
業務割合推計
(当該事務/係全体事務×100)
【勤務時間】 |
10% |
- |
| 定型・非定型業務 |
定型業務 |
| 業務の難易度 |
普通 |
| 活動指標 ※市が何をするか |
| 指標名 |
さわやか相談室相談件数 |
| 単位 |
件 |
指標数値のめざす方向 |
維持 |
| 目標値 |
3520 |
| 目標進捗 |
計画値 |
実績値 |
|
達成率 |
所見 |
| 令和3年度 |
3520 |
4247 |
件 |
120.0 |
% |
時間をかけてじっくりと相談に乗ることができ、情報補収集、教室復帰等に高い効果がある。 |
| 令和4年度 |
3520 |
4408 |
件 |
125.0 |
% |
時間をかけてじっくりと相談に乗ることができ、情報補収集、教室復帰等に高い効果がある。 |
| 令和5年度 |
3520 |
|
件 |
|
% |
|
| 令和6年度 |
3520 |
|
件 |
|
% |
|
| 令和7年度 |
3520 |
|
件 |
|
% |
|
| 指標値の算定・把握方法 |
相談件数を年に3回調査する。 |
| 成果指標 ※市民(市)がどうなったか |
| 指標名 |
いじめの解消率 |
| 単位 |
% |
指標数値のめざす方向 |
増加 |
| 目標値 |
100 |
| 目標進捗 |
計画値 |
実績値 |
|
達成率 |
所見 |
| 令和3年度 |
80 |
77.3 |
% |
96.6 |
% |
積極的な認知と解消率100%を目指し、被害児童生徒の気持ちに寄り添った対応を行う。 |
| 令和4年度 |
80 |
79.8 |
% |
99.8 |
% |
積極的な認知と解消率100%を目指し、被害児童生徒の気持ちに寄り添った対応を行う。 |
| 令和5年度 |
80 |
|
% |
|
% |
|
| 令和6年度 |
80 |
|
% |
|
% |
|
| 令和7年度 |
80 |
|
% |
|
% |
|
| 指標値の算定・把握方法 |
各学校が、毎月提出する「いじめ実態調査」による数値 |
| 事業の評価・改善/実績報告 |
| 実績報告 |
・さわやか相談室の機能充実により、生徒の利用機会が高まっている。
・市内グループウェアを活用し、いじめや不登校に関連する生徒指導個人研修用資料を、市内小・中学校全教職員向けに配信した。
・市内小・中学校児童生徒へ「SOSの出し方に関する教育」について指導した。(夏季休業前) |
| 評価 |
コロナ禍にあり、生徒は様々なストレスを抱える中、さわやか相談室のニーズは高まっている。
いじめを積極的に認知する動向から、教職員個々のいじめに対する危機感が高まってきている。
些細ないさかいも丁寧に対応する組織的指導体制が定着してきた。
児童生徒理解が促進され、温かな学級経営を基盤とし、「居心地のよい規律」を根付かせている。 |
| 今後の方針(改善策) |
表出しにくい「SNSトラブル」に関して、保護者・地域の協力体制の構築が課題である。
11月の「いじめ撲滅運動強調月間」を活用し、学校・保護者・地域の協働連携による取組実践の月間にする。
いじめの捉え方について、教職員・保護者・地域に更なる啓発が必要である。 |
|