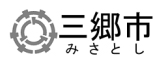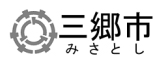| 事務事業名、担当課等 |
| 事務事業コード |
4400061 |
| 事業名 |
認知症総合施策事業 |
総
合
計
画
の
位
置
づ
け |
まちづくり方針 |
7 健やかで自立した生活を支え合うまちづくり |
担当部名 |
いきいき健康部 |
| 担当課名 |
長寿いきがい課 |
| 施策の柱 |
7-2 互いに支え合い、誰もが活躍できる地域福祉のまちを実現する |
開始年度 |
平成21年度 |
| 終了年度 |
なし |
| 施策 |
7-2-2 地域包括ケアシステムの推進 |
| 施策の目的 |
対象 |
高齢者、市民、地域の医療・介護関係者 |
| 意図 |
・誰もが住み慣れた地域で、いつまでも住むことができる |
| 事務事業の目的、概要等 |
何をする事業か
(概要) |
認知症の早期診断・早期対応、重症化予防に向けた支援体制を構築する。また、認知症の容態の変化に応じ、必要な医療、介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、効果的な支援が行われる体制を構築するとともに、認知症ケアの向上を図るための取組を推進する。
|
何の為にやるのか
(目的) |
認知症の人やその家族が安心して生活できる社会の実現。
|
誰・何に対する
事業か
(事業の対象) |
認知症の人とその家族、一般市民、認知症の人と関わる医療や介護等の専門職、地域の団体・企業など
|
目的達成のため、
事業の対象を、
どうしたいのか
(目指す成果) |
・認知症の早期発見・早期対応、重症化予防のための仕組みづくり
・認知症の人の居場所づくり
・認知症の人の支援者のネットワーク形成
・市民の認知症への理解促進
|
| 課題 |
・64歳以下の市民、企業や学校など団体に対する情報発信の不足
・支援の担い手のスキルアップ
・正しい理解が社会全体に浸透していないため認知症バリアフリーが実現していない。
|
| 対応 |
認知症地域支援推進員、地域の専門職や団体と協力し、事業の評価や分析を行いつつ見直しを図る。
|
| 目的を達成することで、市がどうなるか(事業の意義) |
・認知症の人を社会全体で支える仕組みができる。
・認知症の人の社会参加、認知症の人やその家族の居場所ができる。
・市民自ら認知症の重症化予防の行動を取り、認知症になることを予測して自分らしい人生を送るための備えができる。
|
| 歳出 |
| 総事業費(合計) |
実績
|
| 令和5年度決算
|
| 9,050,372
|
| 歳入 |
| 特定財源 |
実績値
|
| 令和5年度決算
|
| 特定財源計 |
9,050,372
|
| 市の実質負担額(=総事業費−特定財源) |
0
|
| 業務分析(量と質) |
|
年間 |
特記事項 |
| 人員(担当) |
フルタイム |
5 |
パートタイム |
1 |
|
業務割合推計
(当該事務/係全体事務×100)
【勤務時間】 |
21% |
- |
| 定型・非定型業務 |
非定型業務 |
| 業務の難易度 |
専門 |
| 活動指標 ※市が何をするか |
| 指標名 |
地域包括支援センター認知症総合施策事業実施回数 |
| 単位 |
回 |
指標数値のめざす方向 |
増加 |
| 目標値 |
18 |
| 目標進捗 |
計画値 |
実績値 |
|
達成率 |
所見 |
| 令和3年度 |
|
|
回 |
|
% |
|
| 令和4年度 |
5 |
|
回 |
|
% |
|
| 令和5年度 |
6 |
3 |
回 |
50.0 |
% |
|
| 令和6年度 |
12 |
|
回 |
|
% |
|
| 令和7年度 |
18 |
|
回 |
|
% |
|
| 指標値の算定・把握方法 |
地域包括支援センター認知症総合施策事業(加算事業)実施件数の合計 |
| 成果指標 ※市民(市)がどうなったか |
| 指標名 |
認知機能検査実施件数 |
| 単位 |
件 |
指標数値のめざす方向 |
増加 |
| 目標値 |
6000 |
| 目標進捗 |
計画値 |
実績値 |
|
達成率 |
所見 |
| 令和3年度 |
|
|
件 |
|
% |
|
| 令和4年度 |
5769 |
|
件 |
|
% |
|
| 令和5年度 |
5800 |
5613 |
件 |
96.7 |
% |
|
| 令和6年度 |
5900 |
|
件 |
|
% |
|
| 令和7年度 |
6000 |
|
件 |
|
% |
|
| 指標値の算定・把握方法 |
認知症チェックサイトアクセス数(家族用・本人用)、認知機能検査実施者件数の合計 |
| 事業の評価・改善/実績報告 |
| 実績報告 |
〇認知症の早期発見・早期対応
・認知症チェックサイトアクセス数 2,705名(家族用)、2,772名(本人用) ・認知機能検査 136名
〇認知症地域支援推進員
・意見交換会 6回
〇認知症初期集中支援チーム
・支援件数 0件 ・訪問回数 0回 ・チーム員会議開催回数 0回
〇認知症初期集中支援チーム検討委員会兼認知症について考える会議(みさとオレンジ会議)
・開催回数3回
〇認知症カフェ 6か所
・実施回数 90回 ・参加者数 754名
〇高齢者等SOSネットワーク
・利用登録者数 80名 ・協力事業者数 81か所 ・見守りシールにて保護 0件 ・発見協力依頼数 3件
〇市民向け講演会
・参加者数 193名
〇チームオレンジ
・チームオレンジ設置数 6か所
〇本人ミーティング
・開催回数 1回 |
| 評価 |
・認知機能検査の市民周知を行い、認知症の早期発見・早期対応の取組みを拡大することができた。
・市民向け講演会を開催し、市民に向けて、認知症についての正しい理解を深める機会を作ることができた。
・認知症カフェ同士の交流会を開催し活動の質の向上を実施した。
・チームオレンジの立上げができた。
・本人ミーティングの開催ができた。
・認知症初期集中支援チーム検討委員会兼認知症について考える会議(オレンジ会議)の開催を増やし、関係機関と話し合う機会を増やした。
・三郷市在住の 65 歳以上の一般高齢者、要支援・要介護認定者、及び介護支援専門員等を対象にアンケ ート調査(令和5年度)では約7割が認知症の相談窓口を知らないという結果だった。
|
| 今後の方針(改善策) |
・認知症の早期発見・早期対応の取組みのさらなる拡大に向けて、市民が検査を受けやすい開催方法の検討や検査実施後のフォロー体制の強化。
・認知症について気軽に相談できる場所を増やし周知する(チームオレンジの推進)。
・本人の声を聞き、認知症施策に反映させる(本人ミーティング推進)。 |
|